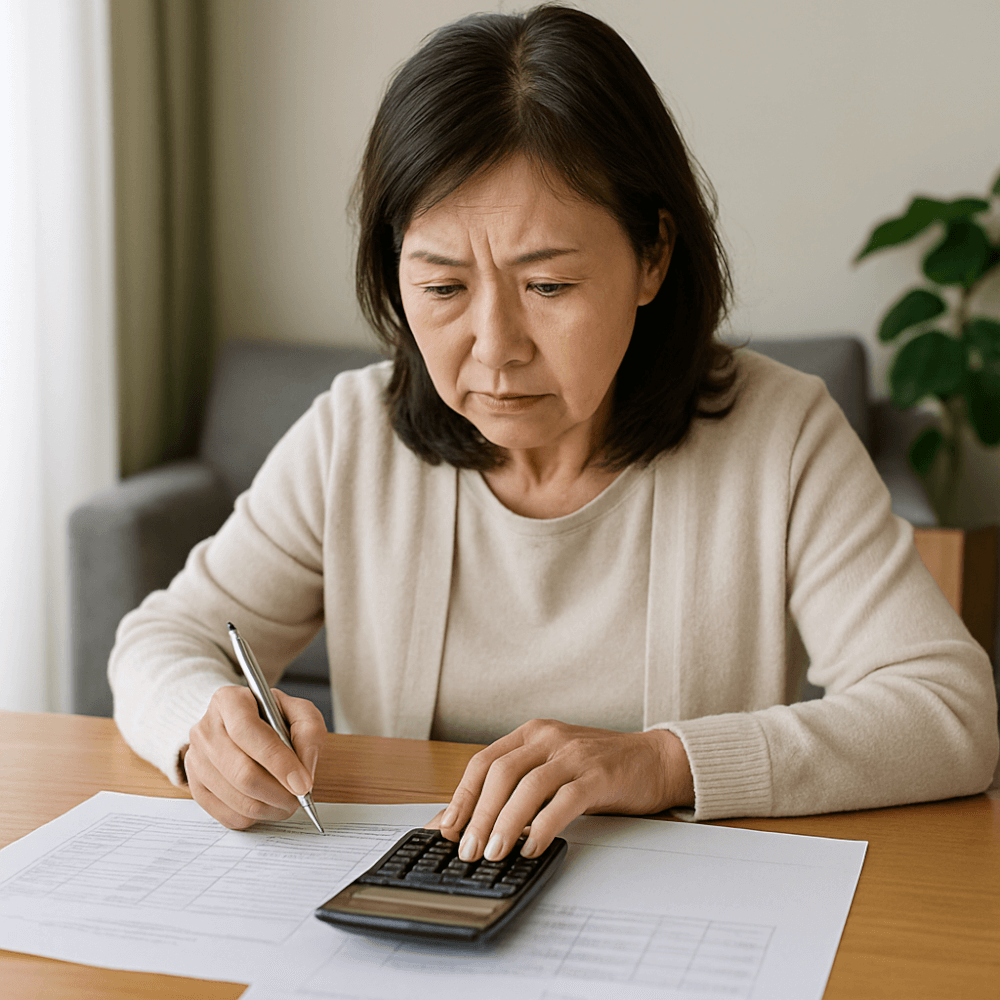「5000万円の遺産を子供2人で相続する場合、相続税はいくらになるのか?」
この疑問を抱え、インターネットで何度も同じ検索を繰り返していませんか。
今や相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、例えば子供2人だけで相続するケースなら基礎控除額は【4,200万円】。実際に5000万円の遺産があると、控除後の課税対象は「800万円」になり、相続税の総額や個人ごとの負担額の計算も複雑です。
「財産の内訳や土地評価額の算定方法、控除や特例がどこまで使えるのかも分かりづらい…」と悩まれる方は少なくありません。「想定以上の税額で損をしたくない」、けれど「どう手続きを進めればいいのか自信がない」という不安もあるのではないでしょうか。
この記事では、相続税のしくみや最新の税制、5000万円を子供2人で分けた場合の計算手順と早見表、見落としやすい注意点まで、専門家監修のもと具体的な実例で分かりやすく解説します。
正確な金額だけでなく、後悔しない相続のための知識も一緒に手に入れましょう。
本記事を最後まで読むことで、あなたの疑問や不安はきっと解消されます。
5000万円の相続税はいくら?子供2人で徹底解説|計算・控除・注意点まで網羅
相続税とは?基本知識と今知っておくべき最新動向
相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続した際に課される税金です。国税庁が定める基準に基づき、相続人が財産を取得する場合に発生します。最近では、基礎控除額の見直しや相続税率の改正が行われており、相続人の人数や遺産総額によって負担額が大きく異なります。税法の変更や特例制度への対応が重要なポイントとなるため、早めに最新情報を把握することが求められています。
以下に主なポイントを記載します。
- 相続税は国税であり、財産の受取時に発生
- 配偶者や子供のみが相続人の場合、基礎控除や特例が適用される場合あり
- 相続税の申告は、死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内が原則
- 基礎控除額や税率は法定相続人の数によって変動
相続税の対象になる財産・資産とその評価方法の詳細
相続税の対象となる財産には、現金や預貯金だけでなく、不動産、株式、生命保険金、車や貴金属、事業用資産なども含まれます。すべての財産が課税対象となるわけではなく、葬式費用や債務など一定の費用は控除可能です。評価額の算出には時価基準や路線価、公示地価などの公的指標が用いられます。
主な課税対象となる財産の一覧
| 種類 | 具体的な例 | 評価方法例 |
|---|---|---|
| 現金・預貯金 | 銀行口座残高、現金 | 残高証明による実額 |
| 不動産 | 土地、建物 | 路線価評価など |
| 有価証券 | 株式、投資信託 | 相続時の時価 |
| 生命保険 | 死亡保険金 | みなし相続財産として加算 |
| 動産 | 車、貴金属、骨董品 | 売却相場、市場価格 |
- 葬儀費用や債務、未払い税金などは控除対象
- 生前贈与やみなし相続財産も注意が必要
- 特定の非課税枠・控除が適用できるケースもある
土地・不動産を含む評価額の具体的な算出方法
土地や不動産は、相続税計算の中で金額が大きくなりやすい資産です。評価は国税庁の公表する「路線価」や「固定資産税評価額」によって算出されます。小規模宅地等の特例により、一定要件を満たす場合は評価額が最大80%減額になる場合もあります。
評価のステップを表で整理します。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 路線価で土地面積を評価 | 年ごとに変更・公式サイト参照 |
| 2 | 固定資産税評価額で建物を算出 | 市町村発行の評価証明が必要 |
| 3 | 小規模宅地特例など適用判定 | 同居や事業用地なら減額可能 |
| 4 | 借地権や借家権なども考慮 | 権利割合に合わせて評価 |
このように、不動産の評価方法や特例制度を正しく理解することで、課税遺産総額を大きく減らせるケースもあります。具体的な評価額や適用の可否は、必ず専門家や税理士に相談することが推奨されます。特に「5000万円の相続税はいくら 子供2人」といったケースでは、この不動産評価が相続税額の決定に直結します。
5000万円の相続税計算|基礎控除・法定相続分・実際の手順
ステップ1:遺産総額・負債・控除の整理と基礎控除額の算出
相続税の計算を正確に行うためには、まず遺産の総額や負債、控除額を把握しておく必要があります。特に基礎控除額は相続税額を大きく左右するため、しっかり確認しておきましょう。
基礎控除の計算式
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基礎控除額 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
子供2人なら基礎控除額は4,200万円となります。遺産総額が5,000万円の場合、課税対象となる金額は
- 5,000万円 - 4,200万円 = 800万円
となります。
財産目録作成のコツと証明書類収集ガイド
財産目録を作成する際は、不動産、預貯金、有価証券などの資産だけでなく、住宅ローンなど負債も正確に把握しましょう。また、評価証明書や通帳コピーなどの証明書類を早めに集めることで手続きがスムーズになります。
- 不動産評価証明書
- 預金通帳コピー
- 株式や投資信託の残高証明書
- 借入金残高証明書
以上を漏れなく準備しておくと、相続税の申告時にも安心です。
ステップ2:法定相続分ごとの配分方法と分割シミュレーション
課税遺産総額800万円を法定相続分に従って分割します。子供2人のみの場合の相続分は等分です。
| 相続人 | 法定相続分 | 配分額 |
|---|---|---|
| 子供A | 1/2 | 400万円 |
| 子供B | 1/2 | 400万円 |
分割例
- それぞれ400万円が課税遺産総額となります。
もし配偶者や兄弟がいる場合は法定相続分が変わるため、「5000万円の相続税はいくら 兄弟」「5000万円の相続税はいくら 配偶者のみ」などで検索し、ケースごとの違いを必ず確認しましょう。
ステップ3:相続税早見表・税率表の見方と実践的な活用
相続税の税率は課税遺産総額に応じて変動します。課税価格が400万円の場合、税率は10%、控除額は0円です。
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| ~1,000万円 | 10% | 0円 |
| ~3,000万円 | 15% | 50万円 |
| ~5,000万円 | 20% | 200万円 |
課税遺産400万円の場合
- 400万円 × 10% = 40万円(1人あたり)
子供2人合計で80万円が相続税の目安となります。
課税遺産総額ごとの総額・分割後の個別税額計算
シミュレーションでもっと正確にみてみましょう。
| 遺産総額 | 基礎控除額 | 課税遺産総額 | 1人あたり課税額 | 1人あたり税額 | 合計相続税額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000万円 | 4200万円 | 800万円 | 400万円 | 40万円 | 80万円 |
この早見表を活用すれば、他パターン(例えば「5000万円の相続税はいくら 子供3人」「1億円 相続税 いくら」)も即座にイメージでき、安心して相続手続きを進めることができます。
ポイント
- 相続税の計算や申告は間違いやすいため、必要時は税理士など専門家へ相談すると安心です。
- 課税額や基礎控除、分割方法などを正確に把握し、適切な準備をすることが大切です。
子供2人で5000万円を相続した場合の実際の計算例と事例
計算例1:子供2人のみで相続した場合の詳細計算手順
5000万円の遺産を子供2人で相続した場合の相続税計算は以下の通りです。
- 基礎控除額の計算
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基礎控除の定式 | 3000万円+600万円×2(相続人2人) |
| 計算結果 | 4200万円 |
- 課税遺産総額の算出
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 相続財産総額 | 5000万円 |
| 基礎控除額 | 4200万円 |
| 課税遺産 | 800万円 |
- 法定相続分ごとの分配額
| 相続人 | 法定相続分 | 各人の分配額 |
|---|---|---|
| 子供1 | 1/2 | 400万円 |
| 子供2 | 1/2 | 400万円 |
- 税率と税額の計算
| 金額 | 税率 | 控除額 | 税額 |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 10% | 0円 | 40万円 |
よって、子供2人がそれぞれ40万円ずつ相続税を納付することになります。合計の相続税額は80万円です。
ポイント
- 子供だけの場合、基礎控除の分配が重要です。
- 早見表や相続税計算シミュレーションの利用も有効です。
計算例2:配偶者+子供2人で相続した場合の具体的な税額
配偶者がいる場合、基礎控除ならびに配偶者控除が適用となり負担が大きく変わります。
- 基礎控除額
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基礎控除の定式 | 3000万円+600万円×3(相続人3人) |
| 計算結果 | 4800万円 |
- 課税遺産総額
| 相続財産総額 | 基礎控除 | 課税遺産総額 |
|---|---|---|
| 5000万円 | 4800万円 | 200万円 |
- 法定相続分で分配
| 相続人 | 法定相続分 | 分配額 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 100万円 |
| 子供1 | 1/4 | 50万円 |
| 子供2 | 1/4 | 50万円 |
- 税率・税額計算
| 金額 | 税率 | 控除額 | 税額 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 10% | 0円 | 10万円 |
| 50万円 | 10% | 0円 | 5万円 |
配偶者控除(1億6千万円まで非課税)があり、通常は配偶者の税負担は0円となります。実際の納税は子供に発生しますが、課税額が低ければ非課税のケースもあります。
ポイント
- 配偶者がいる場合、多くのケースで課税遺産がさらに減少します。
- 配偶者控除の適用範囲内であれば、配偶者の納税義務はありません。
兄弟・親・配偶者がいる場合の税額比較とケーススタディ一覧
下記のように相続人構成ごとに税負担が大きく変わります。
| ケース | 相続人の数 | 基礎控除額 | 課税遺産総額 | 各相続人の法定相続分例 | 税率・税額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子供2人 | 2名 | 4200万円 | 800万円 | 子供1:400万円 | 10%(40万円×2) |
| 子供1人 | 1名 | 3600万円 | 1400万円 | 子供1:1400万円 | 15%(210,000円控除、税額=210,000円) |
| 子供3人 | 3名 | 4800万円 | 200万円 | 子供1人:約66万円 | 10%(6万6,000円×3) |
| 配偶者+子供2人 | 3名 | 4800万円 | 200万円 | 上記参照 | 基本的に配偶者は非課税 |
| 兄弟2人 | 2名 | 4200万円 | 800万円 | 法定相続分:1/2ずつ | 10% |
チェックポイントリスト
- 相続人の人数で基礎控除額が異なる
- 課税遺産総額が少なければ税額も少額になる
- 配偶者控除で大幅な負担軽減が可能
- 相続税は早見表やシミュレーション計算も有効活用
最新の相続税制度や特例を確認するときは、税理士等の専門家への相談も重要です。各種特例や控除適用で納税額は大きく変わるため、必ず事前に確認しましょう。
相続税がいくらまで無税になるか?控除・特例の全知識
基礎控除額・特例制度の基本と最新情報(2025年対応)
相続税がいくらまで無税になるかは、基礎控除額と各種の特例に大きく左右されます。2025年現在の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば「子供2人のみ」のケースであれば、3,000万円+600万円×2=4,200万円が控除対象です。この金額までであれば課税は発生しません。
相続人の人数や関係性により控除額は変化します。
| 相続人 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 子供1人 | 3,600万円 |
| 子供2人 | 4,200万円 |
| 子供3人 | 4,800万円 |
| 配偶者のみ | 3,600万円 |
| 子供2人・配偶者 | 4,800万円 |
相続税の課税対象額=遺産総額−基礎控除額となります。万一、相続財産総額が控除額を超える場合でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを活用すれば大幅に税額が軽減できる可能性があります。
活用例としては、配偶者が実際に相続する財産額が1億6,000万円以下、または法定相続分までであれば相続税がゼロとなり得ます。これら特例制度は状況によって適用要件や申告方法が異なりますので、詳細は税理士等の専門家に確認することがおすすめです。
控除・特例が適用される具体例と申請手順のポイント
主な控除・特例制度と具体例:
- 配偶者の税額軽減
- 配偶者の相続分(法定相続分または1億6,000万円まで)は課税されません。
- 小規模宅地等の特例
- 自宅や事業用の土地は最大80%評価減となる場合があります。
- 障害者控除・未成年者控除
- 相続人に障害者や未成年者が含まれる場合は、一定額を控除できます。
- 葬式費用や債務控除
- 葬儀費用や被相続人の借入金等は相続財産から差し引けます。
申請の主な流れは次の通りです。
- 相続財産の調査・評価を行い、課税対象を確定する
- 基礎控除や各種特例の要否を確認
- 必要な場合、申告書類を作成し、税務署へ相続税の申告・納付(原則として被相続人の死亡から10か月以内)
- 特例を利用する場合は、申告書類に該当資料を添付
ポイント
- 相続人の人数や配偶者の有無によって控除額が変わります。
- 控除や特例を適用する場合、確実な要件確認と書面提出が求められます。
- 節税や申告漏れ防止のため、専門家への相談が有効です。
相続税計算やシミュレーションを行う際は、最新情報や国税庁の早見表を参考にしてください。正確な税額や控除適用には、各ケースに応じた綿密な確認が不可欠です。
相続税申告・納付で失敗しないための注意点と実務対応
相続税の申告や納付は、一度きりの経験となることも多く、失敗やミスを避けるためには正確な知識と準備が必要です。特に遺産総額が5000万円で相続人が子供2人の場合、必要な書類や申告時の注意点、税務署による調査対策について理解を深めておくことが重要です。手続きの流れや、課税対象額の算出、基礎控除の適用も必ず確認しましょう。
相続税申告時の必要書類・手続きの流れ
相続税の申告手続きは多岐にわたり、準備不足では後の修正申告や追加納付につながるリスクがあります。以下のテーブルで、主な必要書類とポイントを整理しました。
| 書類名 | ポイント |
|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本 | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人の範囲確認のため複数通取得 |
| 遺産・財産に関する資料 | 不動産登記簿、預貯金通帳、株式明細、生命保険証券など |
| 固定資産評価証明書 | 不動産の評価額算定に使用 |
| 相続税申告書(一式) | 計算根拠明示・押印必須 |
| 遺言書(ある場合) | 遺産分割協議書の代わりとなる |
| 納税用紙/口座情報 | 納税方法を選択し添付 |
主な申告の流れは次の通りです。
- 遺産内容と評価額の確認(相続財産の洗い出し、評価額を算出)
- 基礎控除額・各種控除や特例の該当確認
- 相続人全員の同意による遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書の作成・添付書類の準備
- 税務署への申告書提出および相続税の納付
申告期限は相続開始(被相続人死亡)から10か月以内です。期限内の納付がされない場合、延滞税や加算税の対象となるため、余裕をもって準備を行うことが大切です。
税務署からの調査や追加調査への備え方
相続税申告後、税務署から問い合わせや税務調査が入るケースがあります。特に預金や不動産の評価、遺産分割、名義預金などは確認対象になりやすいため、正確な記載と客観的な資料の保存が重要です。
よくある指摘ポイントと対処法を以下にまとめます。
- 現金預金の動きが不自然と判断された場合
- 財産の出入記録を通帳や領収書で説明できるように保管
- 不動産評価額の誤りや時価乖離
- 固定資産評価証明書や専門家の評価書を活用
- 生前贈与や名義預金の未申告
- 贈与契約書や贈与税申告書の控えも用意
- 遺産分割協議書と実際の内容に相違がある場合
- 分割協議の記録や、相続人全員の合意書を客観的に準備
調査の連絡がきた場合は、専門家である税理士に相談することで、適切な対応がしやすくなります。税務署からの追加調査にも冷静に証明資料を用意し、正確な説明ができるようにしておきましょう。書類不備や誤った申告内容は、追加の税負担やペナルティ原因となるため注意が必要です。
相続税早見表・シミュレーションツールの活用と比較例
相続税の計算は複雑に見えますが、相続税早見表やシミュレーションツールを活用することで、財産総額や相続人の人数ごとに具体的な金額を簡単に確認できます。特に5000万円の相続財産を子供2人で相続する場合、各自の負担や控除額、実際の納税額も明確になります。さらに、人数や親族構成によって課税額は大きく異なり、シミュレーションの活用が重要なポイントとなります。
主要なシミュレーションツール・早見表の特徴と使い方
相続税のシミュレーションツールや早見表には、財産総額・相続人の人数・配偶者や子供の有無、その他の条件を入力するだけで、課税対象額や税率、実際の相続税額が直感的にわかるものが数多くあります。以下のような特徴があります。
- 手順がシンプル:金額と相続人構成を入力するだけで自動計算
- 控除や特例の反映:基礎控除や配偶者控除など自動で反映
- 複数パターンの比較:家族構成ごとに税額を比較可能
こうしたツールは公式サイトや税理士事務所のホームページで提供されています。課税遺産総額の算出では、相続人の人数・親の有無・兄弟姉妹のみのケース等を入力可能なものが選ばれており、事前シミュレーションで納税額のイメージを持つためにおすすめです。
金額・人数・親族構成による相続税比較一覧
相続税の負担は遺産総額や親族構成によって変化します。ここでは主要なパターン別に、5000万円や1億円を例に相続人の構成による相続税の比較を示します。
| 相続財産総額 | 相続人構成 | 基礎控除額 | 課税対象額 | 一人あたり税額 | 支払う合計税額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000万円 | 子供2人 | 4200万円 | 800万円 | 40万円 | 80万円 |
| 5000万円 | 子供1人 | 3600万円 | 1400万円 | 85万円 | 85万円 |
| 5000万円 | 子供3人 | 4800万円 | 200万円 | 10万円未満 | 20万円未満 |
| 5000万円 | 兄弟2人 | 4200万円 | 800万円 | 40万円 | 80万円 |
| 1億円 | 子供2人 | 4200万円 | 5800万円 | 460万円 | 920万円 |
| 1億円 | 子供3人 | 4800万円 | 5200万円 | 340万円 | 1020万円 |
| 1億円 | 子供4人 | 5400万円 | 4600万円 | 265万円 | 1060万円 |
| 7000万円 | 子供1人 | 3600万円 | 3400万円 | 320万円 | 320万円 |
- 子供2人で遺産5000万円の相続税は80万円。基礎控除4200万円を差し引いた課税遺産800万円を2分割し、それぞれの税率10%で計算
- 子供1人の場合は課税金額が大きくなり、税額も高くなる
- 子供3人や4人の場合、基礎控除が増え、課税対象額そのものが減るため一人あたりの税額も大きく下がる
- 兄弟姉妹のみで相続した場合も仕組みや税率が異なるため、注意が必要
このように各家庭の条件によって納税額は変動します。なお、生命保険金や住宅の評価額・贈与税との違いなども考慮しつつ、最新の相続税シミュレーションを活用することが賢明です。
リスト形式でも主なポイントを整理します。
- 基礎控除の計算は「3000万円+600万円×法定相続人の数」
- 財産額や人数、相続人の種類(子供・兄弟・配偶者など)で大きく金額が異なる
- 早見表やシミュレーションツールで事前に税額の目安を知っておくと安心
- 正確な金額や特例適用の可否は、税理士など専門家へ相談するのが確実
相続・贈与のよくある質問と追加リサーチ項目
5000万円の相続税はいくら?子供1人・3人・兄弟パターン
5000万円の遺産を相続する場合、相続税の計算では「基礎控除額」と「法定相続人の数」が重要です。相続人が子供1人、2人、3人、また兄弟の場合では納税額が異なります。基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で決まり、控除を差し引いた金額に税率を適用します。
| 相続パターン | 基礎控除額 | 課税対象額 | 1人あたりの納税額 | 合計相続税 |
|---|---|---|---|---|
| 子供1人 | 3600万円 | 1400万円 | 85万円 | 85万円 |
| 子供2人 | 4200万円 | 800万円 | 40万円 | 80万円 |
| 子供3人 | 4800万円 | 200万円 | 10万円以下 | 20万円以下 |
| 兄弟2人 | 4200万円 | 800万円 | 40万円 | 80万円 |
相続税率は課税対象額と人数により異なります。子供が多いほど基礎控除が増えるため、相続税の負担が軽減されます。兄弟やその他の法定相続人の場合も同様に計算可能です。
1億円・7000万円・1000万円など遺産規模別の相続税比較
申告の多い金額別に、子供2人が相続した場合の相続税を比較します。
| 遺産総額 | 基礎控除額 | 課税対象額 | 子供2人の合計税額 |
|---|---|---|---|
| 1000万円 | 4200万円 | 0円 | 0円(非課税) |
| 5000万円 | 4200万円 | 800万円 | 80万円 |
| 7000万円 | 4200万円 | 2800万円 | 265万円 |
| 1億円 | 4200万円 | 5800万円 | 690万円 |
ほとんどの場合、1000万円や2000万円規模の遺産は基礎控除以下となり、相続税はかかりません。一方、7000万円や1億円を超える場合は課税割合が増えますので、遺産分割や控除を計画的に検討することが大切です。
贈与税と相続税の違い・計算ポイントと選択肢
贈与税は生前に財産を渡す場合にかかる税金であり、年間の非課税枠(基礎控除:110万円)が特徴です。一方、相続税は被相続人の死亡により遺産を受け取る際に発生し、相続人の人数によって基礎控除額が変動します。
| 比較項目 | 相続税 | 贈与税 |
|---|---|---|
| 課税タイミング | 死亡時 | 毎年課税 |
| 控除額/非課税枠 | 3000万円+600万円×相続人 | 年110万円 |
| 税率 | 10%~55%(課税額で変動) | 10%~55%(額により変動) |
| 注意点 | 申告期限10か月 | 申告が必要(超えた場合) |
贈与税と相続税のどちらが有利かは、金額や受け取り方、時期によって異なります。生前贈与と相続対策には専門家への相談が欠かせません。相続や贈与に関する手続きや費用、申告漏れのリスクにも注意し、適切な対策を検討しましょう。
ポイント
- 相続人の人数が多いほど基礎控除が増え、納税額は抑えられる
- 遺産規模が小さい場合は相続税がかからないケースが多い
- 贈与税と相続税の違いを理解し、それぞれの有利な活用法を把握することが重要
上記をもとに、ご自身の状況に合わせたシミュレーションや専門家への相談も推奨されます。
相続税に強い税理士・専門家への相談と比較ポイント
専門家に相談するメリット・信頼性の高い相談先の選び方
相続税の申告や計算は専門的な知識が求められ、わずかなミスが税額や納付手続きに大きく影響します。このため、経験豊富な税理士や相続専門のプロに相談することで、正確な計算や各種控除制度の利用など、多くのメリットが得られます。
主な相談メリット
- 誤った申告や基礎控除漏れの防止
- 調査・監査時のリスク軽減
- 各種特例や控除の適用アドバイス
- 二次相続や贈与との比較シミュレーション
信頼性の高い相談先の選び方
- 相続税の相談実績が多い税理士事務所を選ぶ
- 過去の相続案件の事例や対応力を確認
- 無料相談や見積もり対応ができるかチェック
- 初回面談時に相談者の状況を丁寧にヒアリングするか注目
表:相談先比較ポイント
| 比較項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 実績・専門性 | 相続税案件数、実務経験年数 |
| 費用 | 着手金、成功報酬の明確性 |
| 初回対応 | 無料相談、事前見積もりの可否 |
| 対応範囲 | 遺産分割・二次相続・事務手続き対応 |
| サポート体制 | 電話・メール・オンライン相談の充実度 |
専門家選びは、費用だけでなく信頼性と実績、提案力で比較検討しましょう。
相談時の準備・必要書類・流れの具体的なガイド
相続税の相談時には、事前準備がスムーズな手続きと正確なシミュレーションの鍵となります。以下に必要な書類や相談の流れを整理しました。
主な準備書類
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺産に関する通帳・不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
- 遺言書や分割協議書(該当時)
- 生命保険・有価証券など財産リスト
相談から申告までの流れ
- 必要書類の収集・整理
- 相続財産の評価・課税遺産総額の計算
- 基礎控除・各種控除特例の適用可否確認
- 相続分ごとの相続税額シミュレーション
- 申告書類作成と提出サポート
- 税額納付・手続き完了
相談当日に慌てないために、事前に手元の資料を揃えておくことが重要です。また、疑問や希望(例:子供2人への分割や二次相続対策など)はメモにまとめて伝えると、より的確なアドバイスが受けられます。
相続税に特化した税理士への相談は、費用対効果や手間の削減、不安解消が期待できる有力な選択肢です。適切な書類と情報を準備して、納得できる申告・相続対策を進めましょう。